
こんばんは。
今日は、ある方からいただいた手紙を紹介したいと思います。
(ご本人と所属機関のご了承をいただきました。ありがとうございます。)
私はフリーランスで仕事をし始めてから、多くの人たちに助けられて今の自分の生活が成り立っていることを実感するようになりました。
そんなこともあり、仕事で得た収入から、自分のできる範囲で、直感的にここだと思ういくつかの団体に寄付をしてきました。
基本的に寄付については自分だけが知っていれば良いと思っているので、公表するつもりはなかったのですが、最近、アフガニスタンの地雷撤去の活動をされている方からいただいた手紙がとても心に残ったのと、私だけに留めておくにはあまりにも勿体ない貴重な内容でしたので、紹介させていただきます。
難民を助ける会(AAR Japan) アフガニスタン事業ご担当者の方からのお手紙
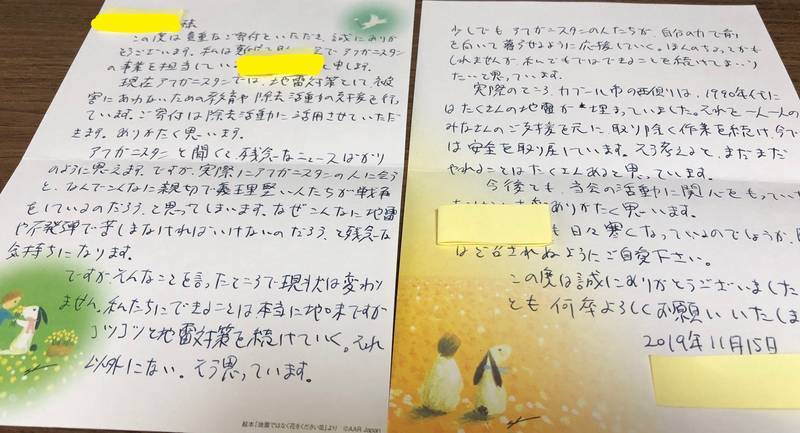
写真の画質を下げて掲載しておりますので、以下に一部抜粋します。
一個人の小額支援者にここまでお手紙いただいたことに感激しました。
現在アフガニスタンでは、地雷対策として被害にあわないための教育や除去活動の支援を行っています。ご寄付は除去活動に活用させていただきます。ありがたく思います。
アフガニスタンと聞くと残念なニュースばかりのように思えます。ですが、実際にアフガニスタンの人に会うと、なんでこんなに親切で義理堅い人たちが戦争をしているのだろうと思ってしまいます。なぜこんなに地雷や不発弾で苦しまなければいけないのだろう、と残念な気持ちになります。
ですが、そんなことを言ったところで現状は変わりません。私たちにできることは、本当に地味ですが、コツコツと地雷対策を続けていく。それ以外にない。そう思っています。
少しでもアフガニスタンの人たちが、自分の力で前を向いて暮らせるように応援していく。ほんのちょっとかもしれませんが、私どもでは出来ることを続けてまいりたいと思っています。
実際のところ、カブール市の西側は、1990年代にはたくさんの地雷が埋まっていました。それを一人一人のみなさんのご支援を元に取り除く作業を続け、今では安全を取り戻しています。そう考えると、まだまだやれることはたくさんあると思っています。
今後とも、当会の活動に関心を持っていただけると大変ありがたく思います。
(出典:難民を助ける会(AAR Japan) アフガニスタン事業ご担当者の方からの手紙 。太字は引用者による。)
添え状にも、貴重な情報が書かれていたので紹介しますね。
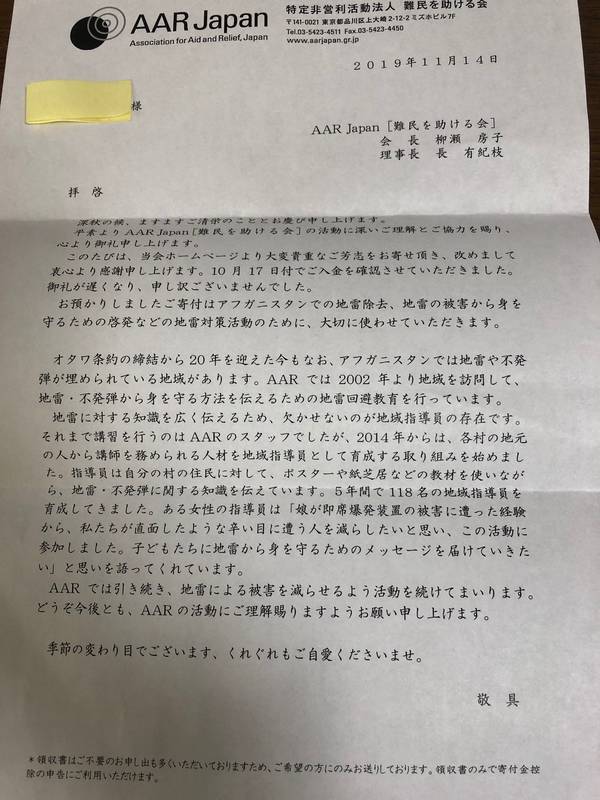
こちらも写真の画質を下げて掲載しておりますので、以下に一部抜粋します。
オタワ条約の締結から20年を迎えた今もなお、アフガニスタンでは地雷や不発弾が埋められている地域があります。AARでは2002年より地域を訪問して、地雷・不発弾から身を守る方法を伝えるための地雷回避教育を行っています。
地雷に対する知識を広く伝えるため、欠かせないのが地域指導員の存在です。それまで講習を行うのはAARのスタッフでしたが、2014年からは、各村の地元の人から講師を務められる人材を地域指導員として育成する取り組みを始めました。指導員は自分の村の住民に対して、ポスターや紙芝居などの教材を使いながら、地雷・不発弾に関する知識を伝えています。5年間で118名の地域指導員を育成してきました。ある女性の指導員は「娘が即席爆発装置の被害に遭った経験から、私たちが直面したような辛い目に遭う人を減らしたいと思い、この活動に参加しました。子どもたちに地雷から身を守るためのメッセージを届けていきたい」と思いを語ってくれています。
(出典:難民を助ける会(AAR Japan) アフガニスタン事業ご担当者の方からの手紙 。太字は引用者。)
以下、私見です。
支援には色々な形があると思いますが、この手紙を読んで、アフガニスタンの方たちの力を信じて、対等な関係で支援活動をされている様子が伝わってきました。
「支援する側が偉く、される側がかわいそうな存在」ではなく、余裕のある側がたまたま困っている側を支援し、応援しているという対等な関係を築かれているように思いました。
また、アフガニスタンの人たちが、自分たちで地雷を回避する教育の仕組み作りがなされていることも、この機会に知れて良かったです。
個人的には、外国からの支援者がいなくなっても、現地で回っていく仕組み作りが大切だと思っているのと、子どもたちへの地雷回避教育は、その子どもが成長して子どもを持った時に(悲しいことではありますが、まだ地雷が残っていれば、)自分の子どもや孫にも学んだ内容を伝えていくことができますよね。
こういう仕組み作りは応援したいなと思っています。
かつてカーブル市の西側に沢山地雷が埋まっていた、それを多くの人の力で取り除いたということも、恥ずかしながら知りませんでした。色々まだ知らないことも沢山あるのでしょうが、ご縁があってこうしてひとつ学べて良かったと思います。
関連リンク 難民を助ける会(AAR Japan) アフガニスタン事業
それでは、また。